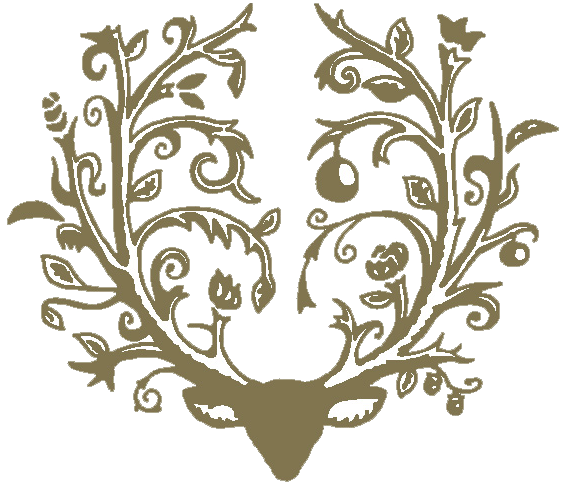農法と農薬と化学肥料の関係

基本的な農法の分類と特徴
有機JAS認証を取得していない生産者は、「有機栽培」や「オーガニック」という言葉を使うことが法律で禁じられています。農産物の認証は国によって異なり、日本では農林水産省の「有機JAS認証」が欧米のオーガニック基準と同等とされています。そのほかにも、「特別栽培・エコファーマー」「自然栽培」などさまざまな農法があります。現在、スーパーなどの小売店に並ぶ農産物は生産性を重視した慣行栽培(現代農法)の農産物が主流です。
<オネストフード&デザイン考える農法の分類>

❶の慣行農法の特徴は効率や生産安定性を重視し、私たちが比較的安価に農産物を手に入れるためには重要です。しかし、そのために病害虫を防ぐために農薬や土に足りない栄養分を化学肥料で補っています。その使用は都道府県によりマニュアル化されています。
❷の減農薬栽培は、都道府県が定める❶の農薬の使用量を半分以下に抑えて、環境負荷を低減し、安全な農産物を生産しようという取り組みです。
❸の有機農法は、国の認証機関が厳しく化学的な農薬や肥料を使うことを制限し、年に1度検査と認証を繰り返す、法律に則った農法で、 認証された事業者のみ「有機栽培」や「オーガニック」という表示を使用できます。
❹の自然栽培は農薬や化学肥料を使用せずに、自然と共存し、自然の力を借りながら、生産者の培ってきたノウハウで、自然に近い形で生産する農法です。
❺の自然農法は農薬や肥料も一切使わない、耕すこともしない。自然に少しの力を貸すだけで農産物を育てる農法で、多少宗教的な側面も持っています。
農薬と化学肥料のメリットとデメリット
農薬や化学肥料という言葉は知ってても、それが農業の現場でなぜ使用されているのか、使用するとどうなるのかなどは案外知らないのではないでしょうか。特徴的なメリットとデメリットをまとめてみました。


農薬や化学肥料はできれば使いたくないとう生産者が殆どだと思います。しかし、経営的な理由や「食糧不足を招かない」という社会的な役割から、今はまだどうしても農薬や化学肥料に頼らざるおえないという事実があります。重要なのは私たちが無関心ではいけないということ。どんな農産物が欲しいのか、食べたいのか。そのための対価をどう考えるのかが重要なのではないでしょうか。
農法を知ると世界が広がる、かも
当然❶の農産物は、生産量が多いため流通システムが流通されているため、価格もある程度抑えられています。しかし、農薬や化学肥料が少なからず使用されています。❷、❸はまだ流通量が少なく生産の手間や生産量が少なくなることでコスト高になります。ただ、昨今ではオーガニック専門に扱うショップなども出てきているので、若い生産者を筆頭に徐々に有機農法への関心が高まってきています。特に❸は農林水産省の「みどりの食料システム戦略」で2050年までに有機農場比率を25%(現在はわずか0.7%程度)まで拡大するという目標を掲げているため、国を挙げた取り組みになっています。❹は農産物に合った適作適地で古くから草生栽培などに取り組み、土がその農産物と共生していて、比較的安定した収量があるところもあります。ただ、産地形成されていないため、価格的には❹と同等レベルのものが多いのではないでしょうか。❺においては一般的に入手するのは困難だと思いますが、例えば重度の添加物過敏症の方には有効な農産物だと思われいます。
上記のように同じ農産物でも農法の違いでさまざまです。何が良くて何が悪いというものではありません。ただ農法の違いを理解して食生活に活かすと、これまで見えていなかった世界が広がってくるかもしれません。